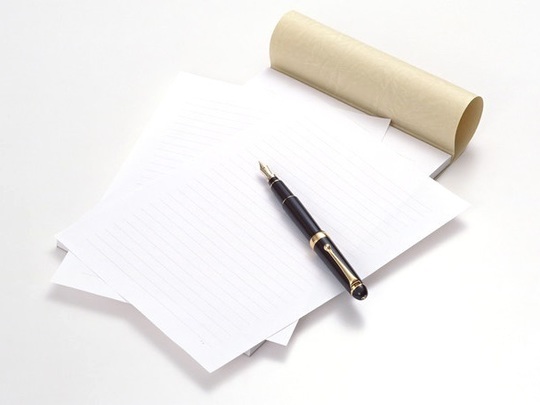内縁の妻(事実婚によるパートナー)の相続手続き
最近では、昔と比較して「事実婚」や「内縁」関係の認知度が増してきたように思います。
さて、では事実婚であるパートナーの相続手続きとは、どのように進められるものなのでしょうか。
事実婚の相続関係
まず、現在の日本の民法の規定においては、いまだ事実婚による相続関係を認めてはいません。
そのため、戸籍において婚姻関係の確認がとれないパートナーにおいては、法定相続人とはならず、関係がない第三者という扱いになってしまいます。
そのため、もし事実婚のパートナーに自分の財産を承継してもらいたいと希望する場合は、遺言書をのこしておく必要があります。
法的に有効な遺言書で、自分の財産の承継者を指定することで、法定相続人とはなれなくても、「受遺者」という立場で、各種相続手続きを進めることが可能となるのです
注意点
その場合にご注意いただきたい点としては、「遺言書は公正証書で残す」ということです。
自筆で遺言書を書いても勿論相続手続きが進められるのですが、「遺言書の検認」手続きをしなければ、各種相続手続きに使用ができません。
その「遺言書の検認」手続きを進めるためにはまず、故人の関係戸籍の収集をしなければなりませんが、法定相続人ではない方が故人の戸籍を収集するのは、容易なことではありません。
そのため、自筆で書かれた遺言書の検認手続きを進めるために、法定相続人以外の受遺者の多くが、司法書士や弁護士等専門家へ費用を支払って、書類の収集をはじめとする手続きの依頼をしているのです。
一方、公正証書でのこした遺言書であれば、裁判所を通して検認手続きをしなくても、相続が発生した時点ですでにその遺言書は法的に有効な書面となっていますので、金融機関等ご自身でも相続手続きを進めることが可能となります。
また、戸籍の収集についても、公正証書で作成された遺言書を提示してみせることで、本来取得権利がない方であっても、受遺者という立場で戸籍の収集が可能となり、専門家に依頼しなくてもある程度手続きを進めることはできます。
また、専門家へ依頼する場合においても、検認手続きの必要がありませんので、必要がある場合と比較すると、その分手数料が安く済む場合もあります。
事実婚のパートナーに遺産をのこす場合、費用も時間も多くかかってしまう自筆証書で遺言書をのこすより、大切なパートナーに手間やお金をなるべくかけさせないよう最後の心遣いとして、公正証書による遺言書作成をご検討ください。
当事務所では、公正証書遺言の作成に関して、無料相談を行なっております。
是非一度、お気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介