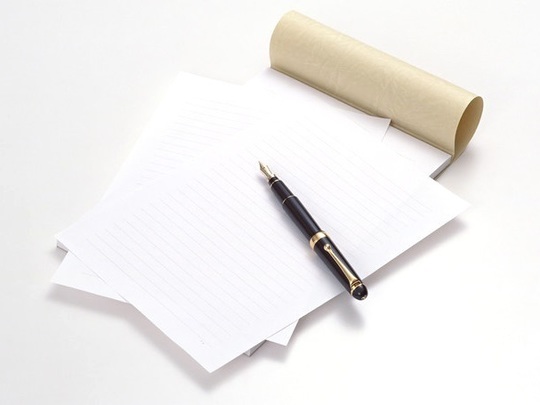相続で必要となる戸籍~出生から死亡までとは
『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2019年6月18日)

「相続手続きで必要になる戸籍はどういった戸籍ですか?」
という質問をよくされますが、
相続手続きで必要となる戸籍は、
その状況によって異なります。
遺言書があるケースでは、遺言者が亡くなったことがわかる戸籍と
承継者として指定されている方の戸籍が主に必要となる戸籍です。
※戸籍に書かれている内容や関係性によっては、別の戸籍が必要になる場合もあります。
遺言書があるケースでも、相続税申告が必要となるケースでは、
相続税の基礎控除額の算出のため、遺言書がないケースと同様に、
遺言者(故人)の出生から死亡までの一連の戸籍のほか、
法定相続人全員の戸籍も必要となります。
遺言書がないケースでは、相続税申告の必要有無は関係なく、
親が亡くなって、相続人としてお子様がいらっしゃるケースの相続であれば、
亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の最新の戸籍が必要となります。
“出生から死亡まで”の一連の戸籍といっても、
正直一般の方にはピンと来ないかもしれません。
一番新しい戸籍をみると、身分事項の欄に、「出生」「死亡」と記載がありますので、
その1通で出生から死亡までのすべての戸籍だろう、
と解釈される方も多いのですが、実際そうではありません。
出生から死亡までのすべての戸籍が1通のみで足りる方は、ほとんどいません。
当事務所でご依頼をお受けしたお客様においても、最低でも2通は必要となっています。
現在20歳以上の方であれば、
すでに出生から現在までで2通の戸籍になっていることが大多数であり、
ご結婚等されていれば、それ以上になっているでしょう。
若くしてご逝去される方においては、その分戸籍の通数が少ないことが多く、
2~3通だけで済むことがありますが、
ご結婚されると新たな戸籍が作られますので、さらに増えることになります。
相続関係が、兄弟姉妹や甥姪まで広がってくると、
上記のような戸籍の収集がその分多岐にわたることとなり、
必要となる戸籍は10通を超えてくることが多くなります。
請求先となる役所もその分多くなりますので、
兄弟姉妹や甥姪までが法定相続人となるようなケースでは、
当事務所のような専門家へ依頼されたほうが、
時間も無駄にかけずに済むほか、心理的にもご負担はかからないかと思います。
ちなみに、一般的には、出生から死亡までの一連の戸籍は3~5通程度となりますが、
転居するたびに本籍地を移しているような方だと、
10通以上も戸籍が必要になったお客様もいらっしゃいました。
離婚歴がある方なども、その分多く戸籍が必要となる可能性があります。
もし本メルマガをお読みの方で、転居するたびに本籍地を転々と動かしている方がいれば、
今後は本当に移す必要があるのか、検討することをおススメします。
また、のこされる相続人のために、生前にご自身の戸籍を取得しておくと、
相続人が戸籍を集めるうえで、同じ戸籍を取得していくだけで収集できることとなり、
専門家へ頼まなくても済むかもしれません。
もし現在、生前対策を進めていらっしゃる方は、対策の一つとして、
ご自身の出生から現在の戸籍を収集することもご検討ください。
なお、当事務所では、相続手続きに必要な戸籍収集代行業務も行なっております。
是非お気軽にご相談ください。
相続のお役立ち情報
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介