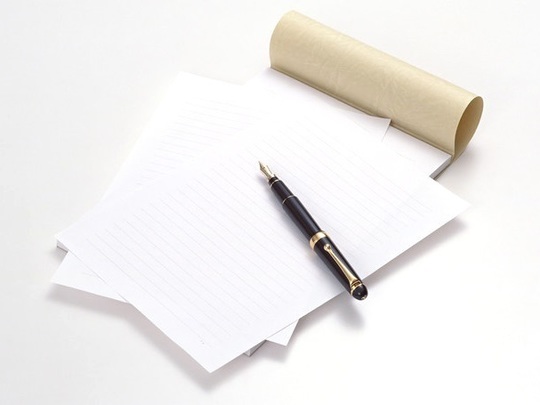タワーマンションで相続税対策する方法・注意点
『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2020年11月10日)

タワーマンションで相続税対策する方法と注意点
タワーマンションを購入すると、
効果的に相続税対策できる可能性があることを
ご存知でしょうか?
特に高額な高層階であればあるほど、
節税効果が大きくなります。
ただしタワーマンションを使った節税対策が行きすぎると
税務署から「否認」されるリスクもあり要注意です。
今回はタワーマンションで相続税対策する方法と注意点をご紹介します。
1.タワーマンションで節税できる理由
タワーマンションで節税できる理由は、
不動産の「相続税評価」方法と関係します。
一般的にマンションの相続税評価額は、
建物部分の評価額と敷地部分の評価額の合計額となります。
建物部分は「固定資産税評価額」で計算し、
土地部分は「相続税路線価」によって計算します。
通常、固定資産税評価額は時価の7割程度、
相続税路線価は時価の8割程度となるので、これだけでも節税になります。
ただしタワーマンションの節税効果は
通常のマンションをはるかに超えるものです。
タワーマンションの時価は、
ご存知の通り高層階になればなるほど上がります。
しかし相続税評価額は「全体面積の割合に応じた金額」になるので、
高層階でも低層階でも評価方法が同じなのです。
たとえば20戸入居しているタワーマンションの場合、
低層階でも高層階でも同じ100分の5(20分の1)の
評価額になるということです。
※税制改正があり、階数によって評価額が変わることに
なりましたがそこまで大きく変わっていません。
実際には高層階の時価の方が極端に高額になるので、
高層階の場合には相続税評価額と時価の差額が大きくなり、
相続税評価額を大幅に下げられる仕組みです。
もしも多額の現預金をお持ちであれば、
高層階のタワーマンションを購入するだけで
相続税額を一気に減額できる可能性があります。
2.タワーマンション節税の注意点
ただしタワーマンション節税を行うときには注意点があります。
それは税務調査において「租税回避行為」とみなされるリスクです。
租税回避行為とは、本来払わなければならない税金を不適切な方法で回避する行為です。
たとえば死亡直前に高額なタワーマンションを購入して相続税評価額を下げ、
少額の相続税を払ってすぐにマンションを売却した場合などには、
租税回避行為とみなされる可能性が高くなります。
タワーマンションで節税対策を行いたいなら、
相続開始より相当早めの段階でタワーマンションを購入して
居住や賃貸などの実績を作り、相続が起こってからもしばらくは売却をせず、
5~6年程度が経過して頃合いを見計らって売却するなどの対応が必要です。
また万一税務調査が入ったときのため、
相続税対策に詳しい税理士に日頃から相談して備えておくと安心です。
当事務所では税理士とも連携して
ケースごとに最適な相続税対策方法をご提案しております。
税務調査への対策も承りますので、
タワーマンション節税に関心をお持ちの方は、是非とも一度ご相談下さい。
相続のお役立ち情報
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介