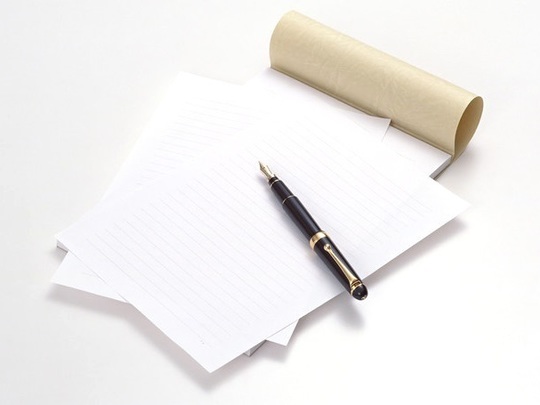古い休眠口座に要注意!
自分の財産、把握できていますか?
『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年9月21日)

昔作った銀行口座で今は全く使っておらず
「放置」しているものはありませんか?
同じ銀行に2つ以上の口座がある場合、
古いものを忘れている方が多いので要注意です。
相続の際、中身が数円だけでも口座があれば立派な「相続財産」。
原則、解約するには相続人全員の印鑑が必要となってしまいます。
遺言書があっても受遺者が単独で預金を取得できなくなるリスクが発生するのです。
今回は銀行口座を放置して
相続人に迷惑をかけてしまうパターンと対処方法を解説します。
相続対策が気になる方は、ぜひ参考にしてください。
1.古い預金口座を忘れているとトラブルに!
昔作った古い口座の存在など、普段は忘れて生活しているでしょう。
このように古くて忘れられている口座を「休眠口座」といいます。
相続時には、古い休眠口座が
トラブルのもとになる可能性があるので注意しなければなりません。
たとえば被相続人AさんがB銀行で2つの預金口座(X口座とY口座)を
持っていたとしましょう。
ご本人は昔作ったY口座の存在をすっかり忘れており、
X口座のことしか頭にありませんでした。
Y口座には3円程度しかお金が入っていない状態です。
Aさんは「B銀行のX口座預金を長男に相続させる」
と遺言書を書きました。
Aさんの死亡後、長男が遺言書をもって金融機関へ行き
「X口座預金の解約払戻を受けたい」と申し出ると、
金融機関は以下のように答えます。
「その方にはY口座もありますね。
こちらについても同時に手続きしていただく必要があります。
Y口座については遺言がないので、
相続人全員の実印による署名押印と印鑑証明書が必要です。」
つまり遺言書があるにもかかわらず、
長男はX口座の預金を受け取れなくなってしまうのです。
他の相続人全員にお願いして
署名押印と印鑑登録証明書を集めなければなりません。
大変な手間になりますし、
協力してくれない相続人がいたらさらに大きなトラブルになるでしょう。
最終的には調停や審判になってしまう可能性もあります。
2.預金口座を把握するために
自分の預金口座を正しく把握できていない可能性があるなら、
金融機関へ問い合わせてすべての口座を開示してもらいましょう。
特に「同じ銀行で2つ以上の預金口座がある場合」に注意が必要です。
・昔取引していた心当たりのある金融機関
・独身時代、旧姓の頃に作った口座
・引っ越し前に使っていた口座
・事業を行っていたときに使っていた口座
こういったものを忘れがちなので注意しましょう。
また遺言書を書くときには、
「〇〇銀行のすべての口座を相続させる」と記載するようお勧めします。
そうすれば「こちらの口座については指定がないので相続人全員の署名押印が必要」
といわれるリスクが低減されるでしょう。
相続対策を誤ると重大なトラブルが発生するリスクが高まります。
不安を感じる場合には、お気軽に司法書士までご相談ください。
まとめ
休眠口座があると相続財産として処理しなければならず、費用がかかったり大変なケースもありますので、気づいたら生前に対応をしておきましょう。
司法書士は不動産と相続の専門家です。
生前対策、遺言書作成、遺産分割に関してお悩みのある場合、お気軽にご相談ください。
相続のお役立ち情報
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介