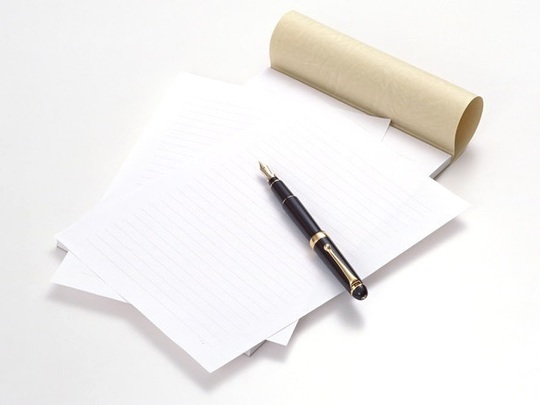資料がない場合の譲渡所得税申告は
専門家に依頼したほうが良い
『相続・遺言ここだけの話』メールマガジンバックナンバー(2021年12月21日)
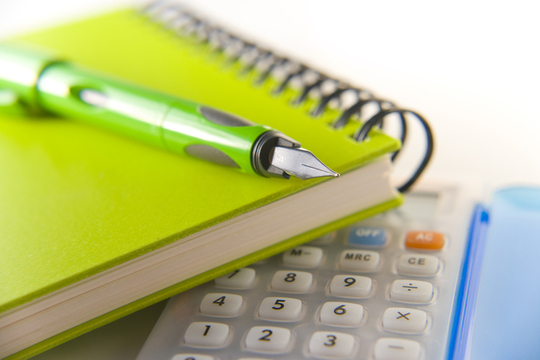
不動産を売却して利益が出たら、
譲渡所得税を申告納税しなければなりません。
このとき「不動産を取得したときの資料」が
残っていなかったら概算の5%しか
取得費用を控除できないので、
税額が高額になってしまうリスクがあります。
そんなとき、税理士に相談すると思ったより譲渡所得税額を下げられるケースも。
相続した不動産の取得費用がわからない方は、参考にしてみてください。
1.記憶に基づいて申告できるケースがある
譲渡所得税計算の際、取得費用に関する資料がなかったら多くの方は
「概算」によって計算します。
概算取得費は「売却代金の5%」になるので、
本当に支払った金額より少額になるでしょう。
それでは控除額が小さくなるので、
結果として譲渡所得税が高額になってしまいます。
実は税理士に依頼すると、
資料が残っていなくても「実額法」で計算できる可能性があります。
資料が残っていないケースでも、税理士が依頼者の
「取得費に関する記憶」に従って取得費用を計算し、
申告書を作成してくれるケースがあるのです。
実は税制上「資料がなかったら概算法を適用しなければならない」
というルールはありません。
概算法はあくまで例外的措置であり、原則は実額法です。
記憶が確かであれば、記憶に従って実額法をあてはめてもかまいません。
2.特殊事情に要注意
資料がなく「記憶」に従って取得費用を計算するときには
「客観的に妥当な価格」にしなければなりません。
たとえば買い急いでいたなどの事情があって通常より高額な価格になっていたら、
通常価額に修正する必要があります。
また後日に修正申告を求められた場合には、
追徴課税が発生するリスクもあるので注意しましょう。
3.間接証拠を探す
取得費用に関する直接証拠がない場合に税理士に譲渡所得税の申告を依頼すると、
「間接証拠」を探します。
・売買時の預金通帳
・振込票
・ローン借り入れに関する資料
・住宅ローン控除の申告書
・当時の日記やメモ
・手帳の記載
・不動産会社から受け取ったパンフレット
こういった資料が取得費用の「間接証拠」となる可能性があります。
4.不動産価格の変動率から計算
不動産価格の「変動率」を使って取得費用の根拠とする方法もあります。
たとえば譲渡時と購入時で不動産の路線価を比べて時価に反映すると、
不動産の取得価額を推計できます。
5.その他の資料や確認方法
不動産を購入したときにお世話になった不動産会社に問い合わせて
取引台帳を出してもらったり、
住宅ローンを利用した銀行から資料を取り寄せたりできる可能性もあります。
法務局で「閉鎖謄本」を取得して抵当権の登記を確認し、
取得価額を推測できるケースも。
以前の所有者を訪問して事情を聞く方法もあります。
まとめ
譲渡所得税に詳しい税理士に依頼すると、
上記のようなさまざまな対応により譲渡所得税を大きく減らせる可能性があります。
資料が残っていない場合には、概算法を適用する前に税理士へ相談してみましょう。
当事務所は相続に特化した事務所になり、相続税に強い税理士事務所と連携して対応が可能ですのでよろしければご相談ください。
相続のお役立ち情報
相続手続きをするときに役立つ相続お役立ち情報です。ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介