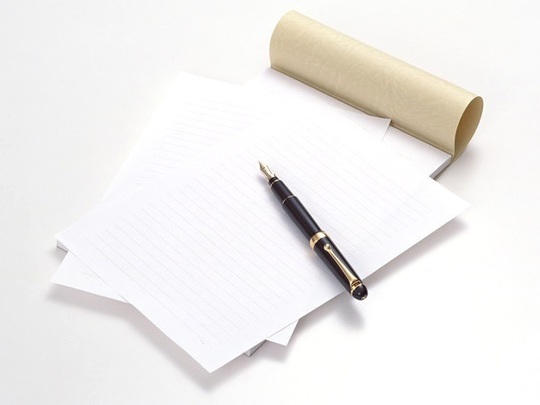刑務所に収監中の相続人が相続放棄をする
家族構成、財産状況など
依頼人:長女
被相続人(亡くなった方):父
法定相続人:長女(依頼者)、長男、二男の計3名
被相続人の負債:約3,000万円
相続手続期間:約2カ月
状況
・父は生前、個人で事業を営んでおり、運転資金として複数の金融機関から計約一千万円程度の借金があった。
また、事業はあまりうまくいっていなかったようで、借金の大部分は返済できていないと聞いていた。父の子である私達姉弟3名は父の死後、相続放棄をすることで意見が一致していた。
・その後、父の存命中に二男が窃盗罪を犯し、刑務所に収監されることになった。収監後間もなく、父が交通事故で事故死した。
父の死後すぐに私達姉弟全員相続放棄を申述(申し立て)をしようとしたが、二男が刑務所に収監中だったため、二男の相続放棄手続きをどのように進めてよいか分からず、今回ご依頼となった。
本件相続放棄手続の問題点
相続放棄は、相続人が「相続が発生し、自分が相続人であることを知った日」から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の意思を書面で申し述べ、家庭裁判所の審査を通過した上で、相続人が相続関係から離脱するという制度です。
そして、家庭裁判所に提出する書面においては、相続放棄の意思を表明するものとして、相続人自身の署名と捺印を要求しています。
今回のケースでは、相続人はみな期限内での手続きを心がけており、期限を過ぎてしまうことにより相続放棄が認められない、というような事態は免れそうです。
しかし、問題は二男の相続放棄の書面の内容です。
書面には通常、相続人の捺印が必要ですが、受刑者は刑務所内に自身の印鑑を持ち込むことはできません。
また、相続人が相続放棄の申述をした場合、家庭裁判所は審査の一環として相続人の自宅へ「照会書」、「回答書」といった書面を送付し、相続人の意思や相続人が相続放棄制度を理解しているか確認を行うことが一般的ですが、相続人が刑務所に収監されている場合、この書面の受取りをどうするか、といった問題が出てきます。
以上のような問題に対処するため、以下のように手続きを進めました。
ご依頼後の相続手続き
各相続人への相続放棄の意思確認
相続放棄の申述は、各相続人が相続放棄を行う意思を持って行わなければなりません。
相続人の意思に反する相続放棄は、たとえそれが家庭裁判所に受理されたとしても、後に取り消される可能性があります。
このようなリスクを回避するため、各相続人への意思確認は最も重要な手続きとなります。
本件では長女、長男とは実際に面談し、各人の相続放棄の意思を確認しました。
一方で、二男は遠方の刑務所に収監中であり面談時間の確保が難しかったため、弊所から刑務所へ手紙を送り、書面による相続放棄制度の説明とともに二男の相続放棄の意思をしっかりと確認しました。
相続放棄申述書の作成
相続放棄の申述は相続放棄申述書という書面で行います。書面に記載する内容には、亡くなった方や相続放棄をする相続人の本籍・住所等のほか、亡くなった方の死亡をいつ知ったのか、亡くなった方の財産や負債の状況をどの程度知っていたのか、相続放棄をする理由などがあります。
こちらもやはり二男の申述書の記載内容が問題となります。
まず、二男の住所欄には刑務所の住所を記載し、刑務所の「在所証明書」も添付してもらいました。
相続放棄申述書に相続人の住所を記載する理由は、前記の「照会書」や「回答書」といった書面や、相続放棄が受理された後に郵送される「相続放棄申述受理通知書」の送付先を明示することにあります。
もし二男の住民票上の住所を記載してしまうと、二男はいまだ刑務所に収監中であるため、次男が上記書面を受け取ることができなくなってしまいます。
※「在所証明書」とは、受刑者が刑事施設に収容されている事実と期間を証明する書類です。
また、相続放棄申述書には相続放棄を申述する相続人の捺印が必要です。
しかし二男は収監中のため、印鑑を所持していません。
そこで、申述書には二男の拇印を捺してもらい、「刑務所長の奥書証明」を添付してもらいました。
※「刑務所長の奥書証明」とは、受刑者が確かに自身の拇印を捺印したことの証明書です。
さらに、亡くなった方の財産状況をどの程度知っていたか、その財産を消費したりはしていないか等、相続放棄を受理してもらうために重要な事柄を手紙を用いてしっかりと確認することが必要です。
戸籍や住民票等の必要書類の収集
相続放棄を家庭裁判所に申述する際には、亡くなった方や相続放棄をする相続人の戸籍や住民票が必要となります。
本件の場合、長女から戸籍や住民票取得用の委任状に署名捺印をもらうことで、弊所ですべての必要書類を収集しました。
相続放棄申述書面を裁判所へ提出
各相続人の相続放棄申述書や戸籍、住民票等がそろい、家庭裁判所へ書類一式を郵送し、相続放棄を申述しました。
この書類一式の中に1点特別な書類を追加しました。それは家庭裁判所に対する「上申書」という書類です。
「上申書」とは、様々な事情を抱える相続人の事情を考慮して、通常の手続を緩和してもらったり、省略してもらったりするための、いわばお願いをする書面という意味です。
本件では、二男が事情により、家庭裁判所から送られてくる書類に対して迅速に対応することが困難な状況でした。
そこで、家庭裁判所からの「照会書」や「回答書」の二男への郵送を省略してもらえるよう、上申書を追加したのです。
なお、上申書はあくまでも家庭裁判所に対して手続の一部の省略をお願いする文書のため、代わりに詳細な申述書を作成することが重要です。
各相続人への相続放棄申述受理通知書の到達
家庭裁判所への申述から約3週間後、長女と長男から「相続放棄申述受理通知書」が自宅へ届いたとの連絡を受けました。
「相続放棄申述受理通知書」とは、家庭裁判所が相続放棄の申立を受理した場合に発行される書類です。
再発行不可の書類ですので、大事に保管しておくことが重要です。
家庭裁判所も二男の状況を考慮し、「照会書」等の書類送付手続を省略しても問題なしと判断したようです。
他の相続人から数日遅れて、二男のもとへも「相続放棄申述受理通知書」が届いたと長女から
連絡を受けました。
この各相続人の「相続放棄申述受理通知書」の到達をもって相続放棄手続きは終了となります。
相続放棄手続きが完了
特別代理人の選任から不動産の名義変更、預貯金解約等の完了まで2ヶ月ほどお時間を頂戴しました。
不動産の名義変更後の書類や金融機関の相続手続書類等、ご返却可能な資料を相続人の方へすべてご返却し、相続手続きは完了しました。
なお、本件の特別代理人の権限は、遺産分割の範囲に限られていたため、相続手続きの完了とともに特別代理人の権限も消滅しました。
本件のように、通常人と異なり、コミュニケーションが制限される状況にいながら、相続放棄の手続きを行う必要がある方もいらっしゃいます。
そのような場合、その方の放棄意思や制度理解の確認はいくら行ってもやり過ぎということはありません。
相続放棄を受理するのは家庭裁判所である以上、裁判官を納得させるため、相続人の放棄意思を反映させた詳細な申述書の作成が重要であると感じました。
また、相続放棄の申述に必要な書類にしても、通常の相続人の書類とは異なる書類が必要とる場合があります。
そのため、普段から相続放棄に関する情報収集に努め、どのようなケースにも対応できるよう心がけておく必要があると体感しました。
相続手続きのお役立ち情報
相続手続きに役立つ情報となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介