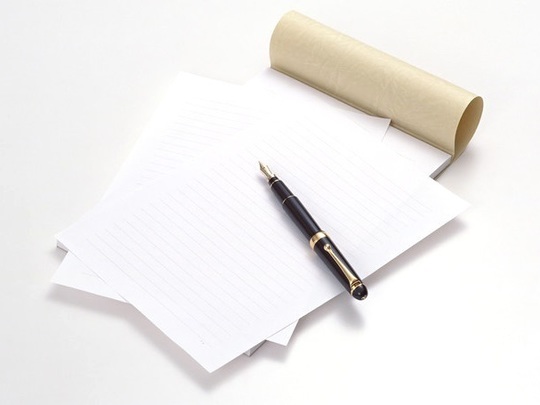相続放棄の申し立ての期限は、結局いつから3ヶ月以内なの!?
家族構成、財産状況など
【ケース1】
依頼人:養女
被相続人(亡くなった方):養父(令和6年12月死亡)
法定相続人:養女のみ
被相続人の負債:約1,000万円
相続手続期間:約1カ月
(状況)
・養父は平成30年頃に茨城県から長野県に移住しており、茨城県の自宅は移住の際に処分したものと思っていた。
その後、令和6年12月に養父が亡くなり、親族に念の為茨城県の不動産の所有者を調査したほうがよいと言われ、令和7年2月に不動産を調査したところ、名義が養父のままであることが発覚した。
なお、養父には当該不動産の他に、預貯金など遺産と呼べるものは全くない。
・令和7年4月に親族から、養父が叔父から1,000万円の借入をしている旨を告げられ、その際に交わした金銭消費貸借契約書も提示された。
養父に負債があることは今回の契約書の提示され初めて知った。
・自分が養父の相続人であることは、養父が死亡した時から知っていた。
・負債の存在が新しく発覚したため、相続放棄をすることに決めた。
【ケース2】
依頼人:孫
被相続人(亡くなった方):祖父(昭和63年11月死亡)
法定相続人:孫2名
被相続人の負債:不明
相続手続期間:約1カ月
(状況)
・祖父は依頼人の祖母と早くに死別し、その後再婚し、後妻と長く連れ添ったと親から聞いていた。依頼人は祖父とは疎遠な関係であり、上記事情により祖父の遺産はすべて後妻や後妻との間の子供に渡ったと思っていた。
そんな折、令和6年12月の暮れに自宅の大掃除をしたところ、押し入れから不動産の権利証が出てきて登記事項証明書を確認したところ、祖父名義のままになっている不動産があることを知った。
・祖父は40年近く前に亡くなっており、後妻の家族とも没交渉の状態となっているため
、不動産の他に祖父の財産・負債があるかどうかは全くの不明である。
・孫2名の両親は祖父の死後に相次いで死亡しており、孫2名とも自身が祖父の相続人であることは何年も前に知っていた。
・祖父の負債については全くの不明だが、疎遠な関係を考慮し相続関係から離脱するため、相続放棄を決断した。
相続放棄ができる期間
・原則
民法では、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知った時(以下「起算日」といいます)」から3ヶ月以内に、相続放棄の申し立てを行うべきと言っています。
この「起算日」は、もう少しわかりやすく言うと、「被相続人が亡くなったことを知り」かつ「自分が相続人であることを知った時」と解されています。
【ケース1】も【ケース2】も、相続人は被相続人が死亡したことは過去にすでに知っており、また、自分は被相続人の子又は孫であり、自分が相続人であることは以前から知っていました。
よって、両方のケースとも起算日から3ヶ月以上経過しているため相続放棄はもはや認められないのではないか、と考えられます。
・例外
通常、亡くなった人に財産や負債があることを知っていれば、相続人は相続又は相続放棄することを自然に選択すると思います。
しかし、亡くなった人の生前の状況から、その人が全く財産を持っていないと判断される場合や、相続人が亡くなった人と疎遠な関係で、財産・負債の状況が全く不明な場合があります。
今回ご紹介した【ケース1】は財産・負債が全くないと思っていたケース、【ケース2】は財産・負債が全くの不明だったケースに該当します。
このような場合、相続人はわざわざ手間のかかる相続手続又は相続放棄手続を行うでしょうか?
全員とは言いませんが、おそらく手続を放置する相続人も一定数いることでしょう。
このように、亡くなった人の財産・負債に対する認識が無い、または不明の場合、例外的に、財産・負債の存在が判明した時を起算点とすることができます。
つまり、【ケース1】では不動産の存在を知った時(令和7年2月)、【ケース2】では同じく不動産の存在を知った時(令和6年12月)を起算点とし、それぞれ起算点から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てれば相続人は相続放棄できるということになります。
家庭裁判所からの質問と回答
家庭裁判所に対して相続放棄を申し立てると、裁判所は通常、相続放棄を申し立てた相続人に対して、相続放棄は自分の意思で行っているのか、相続放棄の制度をちゃんと理解しているか、といった質問を書面で送ってきます。
相続人はその書面に回答を記載して裁判所へ送り返すことで裁判所は最終的に相続放棄を受理してよいかどうか判断します。
そこで、今回ご紹介したような例外的なケースの場合、裁判所からの質問が通常の放棄手続きよりも複雑になることがあります。
家庭裁判所に対して相続放棄を申し立てると、裁判所は通常、相続放棄を申し立てた相 実際に【ケース1】、【ケース2】ともに、詳細な質問事項が相続人に対して寄せられました。
主に亡くなった人の財産状況は知っていたか、財産状況を知らなかった場合や不明な場合は、その理由等を突っ込んで聞いてくる印象です。
このような質問に的確に回答するためにも、相続人に対して相続放棄の制度を詳しく説明し、理解していただくことが何よりも重要となります。
いままで数多くの相続人様のお話をお聞きしてきましたが、相続放棄に関しては、いかなる場合も「被相続人の死亡から3ヶ月以内に申し立てしなければならない」という認識の方がかなり多くいらっしゃる印象です。
しかし、相続放棄の制度は、原則、相続人を守るための制度です。相続人にもそれぞれ事情がありますので、裁判所もその事情を考慮してなるべく柔軟に対応するよう努力しています。
もし相続放棄をお考えの相続人様で、事情により断念せざるを得ない、といった状況の方がいらっしゃいましたら、弊所へお電話をいただき是非お話をお聞かせください。
もしかしたらお力になれるかもしれません。
相続手続きのお役立ち情報
相続手続きに役立つ情報となります。
ご参考にしていただければ幸いです。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介