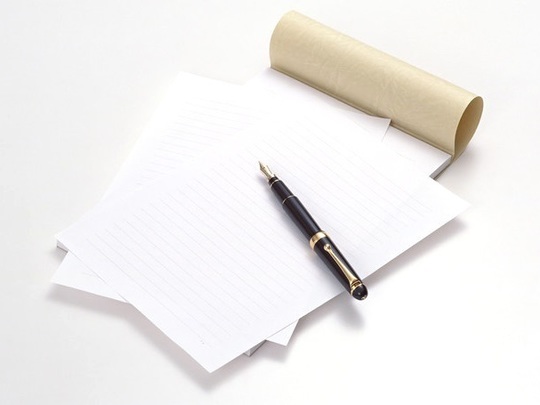相続税の各種控除を利用すれば税金が減ります
(1)相続税の基礎控除
相続税の計算をする際には、かならず相続財産(遺産)の金額から控除されるものがあります。
それを相続税の基礎控除といい、これは大きな額になります。この基礎控除額内で遺産が収まるケースが約90%と言われています。
相続税の基礎控除額
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
※令和3年11月現在。
(2)配偶者に対する相続税の控除
配偶者が、法定相続分または1億6,000万円以下の遺産を相続する場合は相続税がかかりません。
相続税の控除の中でも最も大きな控除です。
(3)小規模宅地等の特例
居住用や事業の不動産で相続人が継続して利用する土地について、小規模宅地等の特例が適用されれば、土地の評価額が最大80%下げることができます。生前対策として、この特例をうまく使うことで相続税を大幅に減らすこともできます。
《例》
1億円の土地全体に小規模宅地等の特例が適用できれば、相続税の計算上では土地評価額が2000万円になります。8000万円の控除を受けられます。
(4)死亡保険金控除
相続人で死亡保険を受け取る場合は、生命保険金控除があります。控除される額は、『法定相続人数×500万円』となっています。
《例》
死亡保険金が1200万円で法定相続人が2名の場合は、相続税の課税対象となりません。
1200万円 − (500万円 × 2) = 200万円
※1200万円の死亡保険金を受け取っても、相続税は200万円にしか課税されません。
(※)適用不可となるケースがあります。
家庭裁判所による相続放棄をした人が受取人の場合は適用できず控除されません。1000万円の死亡保険金を受けとった場合、1000万円全額が遺産として課税対象となります。
(5)死亡退職金控除
《例》
死亡退職金が600万円で法定相続人が1名の場合は、100万円のみ相続税の課税対象となります。
600万円 − (500万円 × 1) = 100万円
※600万円の死亡退職金を受け取っても、相続税は100万円にしか課税されません。
(※)適用不可となるケースがあります。
家庭裁判所による相続放棄をした人が受取人の場合は適用できず控除されません。600万円の死亡退職金を受けとった場合、600万円全額が遺産として課税対象となります。
(6)贈与税(暦年課税贈与)額控除
被相続人が死亡する前の3年間(※)に相続人が贈与を受けた財産は、そのままにしておくと相続財産にプラスされて課税対象となります。
ただし、しっかり贈与税を支払ったにもかかわらず、相続財産として相続税が課税されることになると贈与のときと相続のときで2度課税されることになってしまいます。
そのため、贈与があったときに相続税の前払いのように贈与税を払っていると考えて相続税から控除することが可能です。
つまり、贈与税と相続税を二重にかかることを防ぐために、この贈与税(暦年課税贈与)額控除があります。
(※)暦年贈与については、制度の改正に伴い、令和6年1月1日以降の贈与から持ち戻し期間が異なります。持戻金額にご注意ください。
(7)贈与税額控除(相続時精算課税)
相続時精算課税贈与税を支払っている場合は、相続のときに相続税額から控除します。
この制度も、贈与税と相続税を二重でかかることを防ぐためにあります。
また、贈与を行なった際に贈与税を多く払いすぎている場合がありますが、その場合は相続税申告を行なって贈与税で多く払いすぎた分の税額の還付してもらうことが可能です。
(8)未成年者控除
未成年者の相続人がいる場合には、6万円に相続人が20歳に達するまでの年数を乗じた額を相続税額から控除することができます。
6万円×(20歳−相続開始時の年齢)
※平成24年4月現在。今後変更される可能性があります。
《例》
8歳の子が相続する場合は、72万円が税額控除されます。
6万円 × (20歳 − 8歳) = 72万円
(9)障害者控除
相続人が精神・身体に障害ある者(一般障害者)の場合には6万円、精神・身体に重度の障害ある者(特別障害者)の場合には12万円に対して、相続人が70歳に達するまでの年数をかけた額を相続税額から控除することができます。
6万円(特別障害者は12万円)×(70歳−相続開始時の年齢)
※平成24年4月現在。今後変更される可能性があります。
《例》
30歳の一般障害者が相続をする場合は、240万円が税額控除されます。
6万円 × (70歳 − 30歳) = 240万円
(10)相次相続控除
例えば、夫が亡くなって、10年以内に配偶者が亡くなることはよくあるケースです。
このような10年以内に相続が続けてある場合、2回目の相続のときに 1回目に支払った相続税の一部を差し引くことが可能です。
(11)外国税額控除
外国に財産を持っていた場合は、外国で相続税にあたる税金を支払わなければいけないことがあります。
そのような場合は、外国で支払った税金を、日本の税金から差し引くことが可能です。
相続税お役立ち情報はこちらから
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介