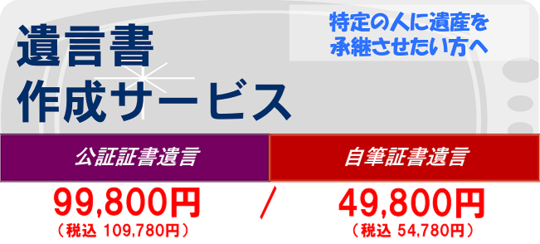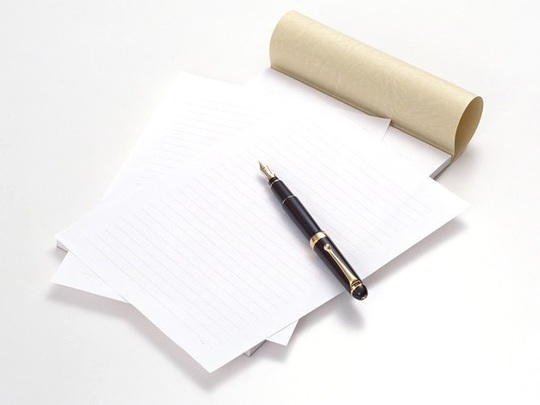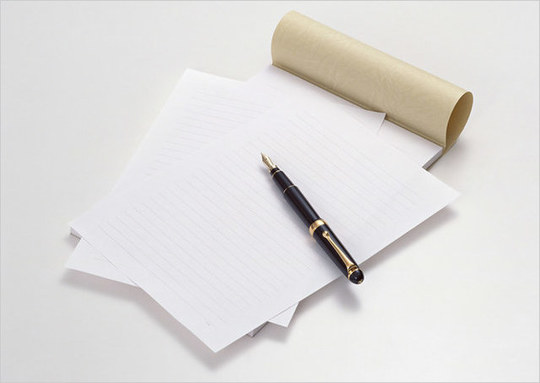遺言書でできること
相続の生前対策として多くの方が思い浮かぶのが「遺言書」の作成だと思いますが、遺言書に書くとどんなことでもできるのでしょうか。
遺言書に書いてはいけないことが法律で決められているわけではありませんが、遺言書に書いても、いざ相続が発生した際に法的効力がないものもあるので、その場合は遺言書の内容が実現されない可能性があります。
せっかく遺言書を残すのであれば、法的効力があることに重点をおき、その他、相続人に「こうしてほしい」という希望があれば「付言事項」として残すとよいでしょう。
それでは、遺言書でできる主なことについて説明していきます。
相続人以外の人へ相続財産をわける
相続人ではないけれど生前にお世話になった方など、自分の遺産をわけてあげたい方がいる場合は、遺言書に書くことでその方へ財産分与することができます。これを「遺贈」と呼びます。
相続分の指定
相続人には「法定相続分」という民法で定められた相続割合があります。しかし、これはあくまでも相続できる権利として定められているものなので、法定相続分と異なる割合で相続してもまったく問題ありません。
もちろん、その場合は相続人全員の承諾が必要となります。
しかし、遺言書では相続分の指定ができるので、「相続人Aには10分の7、相続人Bには10分の3を相続させる」と法定相続分とは異なる相続割合で指定することができます。
相続財産を相続人ごとに指定
不動産、預貯金、株など、複数の財産を所有している場合は、遺言書がないと誰が何を相続するのかは相続人同士で話しあって決めなくてはいけません。
たとえば、生前に口頭で「不動産はお母さんに相続させるように」と約束しても、自分の死後では本当にそのように実現してもらえるのか見届けることができません。
「不動産は相続人A、預貯金は相続人Bへ相続させる」など、遺言書で相続させる財産を指定することで自分の希望に沿って相続財産を承継させることができます。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために相続手続きを遂行する人です。遺言執行者は民法で定められた権限が与えられるわけですが、他の相続人に対して速やかに行わなければいけないこと(遺言執行者に就任したことの報告、財産目録を交付など)が義務付けられています。遺言書に遺言執行者の指定がなければ、相続発生後に家庭裁判所による遺言執行者選任の手続きが発生しますので、遺言書を作成するのであれば遺言執行者を指定しておいた方がよいでしょう。
その他、遺言書でできることは次のとおりです
- 福祉施設や団体などへの寄附
- 未成年後見人の指定
- 婚外子の認知
- 相続人の廃除および廃除の取り消し
- 特別受益(生前贈与や遺贈)の持戻し免除
- 遺産分割の禁止
- 相続人の担保責任の免除・減免
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介