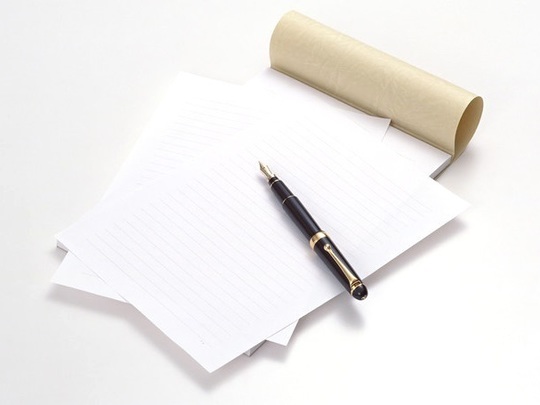遺産分割がまとまらない場合の解決方法 調停
調停は家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入って
遺産分割の話し合いをまとめていきます。
調停とは
調停とは、家庭裁判所で調停委員である裁判官が1人と調停委員が2人以上が間に入り、各相続人の客観的で妥当な相続分を割り出し指導してくれる手続きです。
調停手続きの流れ
裁判所への申立て

相続人の中の1人もしくは数人が他の相続人全員を相手として、相手方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てによって手続きが始まります。
相続人全員に【照会書】が届くので返送する

家庭裁判所は調停の申立てを受けると、相続人の親族関係や相続財産などの状況を確認するために照会書という書類を相続人全員に郵送します。
相続人は、この照会書に回答することになり、家庭裁判所はこの照会書の回答をもとに資料を作成して、家庭裁判所で調停手続きが始められます。
家庭裁判所が事情の聞き取りや指導
家庭裁判所では、調停委員が相続人からそれぞれ個別に話を聞き、相続人同士で遺産分割ができるように指導したり客観的で妥当な結論に導いていくようにして調停委員全員で相続人全員へ働きかけることになります。
調停委員は相続人の希望や経緯や事情についての話を聞き、1ヶ月に1度のペースで面談をして相続人それぞれと指導を繰り返していきます。
そして、この遺産分割調停手続きは、弁護士が代理人となっている場合でも、相続人本人が出席するのが原則とされています。
なぜかというと、相続争いの原因が相続人間の事情に及ぶことが多く、弁護士に聞いても詳しい内容が分からないことがあるからです。
調停成立

調停手続きを進めて相続人同士で合意できた場合は合意した内容を【調停調書】に記載することで調停成立となります。
この調停調書は確定判決と同様に考えられているので非常に重要な書類となります。
そのため、不動産名義変更(相続登記)も調停調書の謄本で手続きが可能です。
調停で成立しなかった場合
調停手続を進めても、相続人間で話し合いがまとまらに場合は、調停不成立となり、家庭裁判所で自動的に審判手続きに移行することになります。
調停手続きにおける詳細
申立人
- 相続人
- 遺言執行者など
費用
- 相続人1人につき収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(金額はそれぞれの裁判所により異なります)
一般的な必要書類
- 調停申立書
- 被相続人(亡くなった人)の全ての戸籍など
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍の附票
- 遺産(相続財産)に関する証明書(不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書等)
書類を提出する裁判所
- 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介