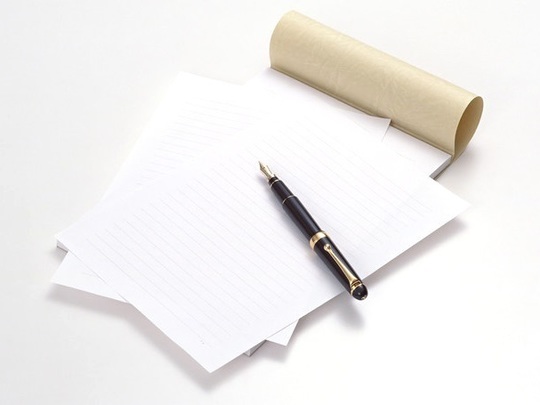遺産分割がまとまらない場合の解決方法 審判
審判は、モメている相続人に家庭裁判所が
遺産分割割合を決めることです。
審判とは
手続きの流れ
調停不成立で審判手続きに移行

これは改めてなにか特別な手続きをしなくとも調停手続きが不成立となると自動的に移行することになります。
調停を行なわずに初めから審判の申し立てを行なうこともできますが、実際には、家庭裁判所がまずは調停手続きを進めなさいと、職権で調停手続きにされることがほとんどのようです。
審判手続き開始

審判は裁判手続きではありますが、一般公開されるものではなく非公開で行なわれます。
調停の手続きのように相続人一人一人、個別に話を聞くわけではなく、期日に相続人全員が裁判所に集まり、裁判官が進行して手続きをしていきます。
自分の主張したいことがあれば、書面にした上で証拠書類も添付します。
1回目で終わらなければ2回、3回と続いていきます。
審判(裁判所が決定を下します)
最終的に、裁判官は職権によって証拠尋問、証拠調べ、相続人や相続財産の確定を行ない、 それぞれの相続分に応じた分割方法の決定を下し、審判書を出します。
実際、ほとんどのケースでは、各相続人それぞれの法定相続分で審判が終わるようです。
この家庭裁判所の審判書には、強制力があり、相続人同士での合意ができない場合も、この審判書に従わなければなりません。
不服申立
しかし、家庭裁判所で出された審判の結論に不服がある場合には、家庭裁判所から審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へ行うことができます。
即時抗告をすると、次は高等裁判所での審理が始まり、問題の解決を図ることになっていきます。
争い事を避けるために
両親などの介護をしていた相続人や会社の事業後継者となる相続人が家庭裁判所で審判手続きをしているのを見たりすると、被相続人(亡くなった方)が遺言書を用意することで、相続人同士の争いにならずに相続問題は解決していたはずだ、と感じることがよくあります。
生前仲が良く、争いなど絶対に起こらないと思っていた親族同士も、自分が亡くなってから突然不仲になるケースがあります。
自分の死後、家族が困らないように準備できることがあります。
ご不明な点がありましたらご相談ください。
審判手続きにおける詳細
申立人
- 相続人
- 遺言執行者など
費用
- 相続人1人につき収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手(金額はそれぞれの裁判所により異なります)
一般的な必要書類
- 調停申立書
- 被相続人(亡くなった人)の全ての戸籍など
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票又は戸籍の附票
- 遺産(相続財産)に関する証明書(不動産登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書等)
書類を提出する裁判所
- 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介