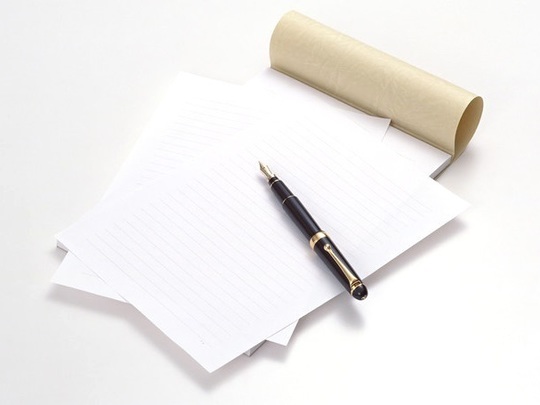遺言を確実に実現させるために
注意するべき3つのポイント
遺言執行者を定めておく
「遺言執行者」とは遺言書に書かれた内容を実現させる人のことです。
自筆証書遺言(自分で全文を自署する遺言形式)においては、この遺言執行者を指定されていないことが多いのですが、実はせっかく遺言書を残しても遺言執行者が指定されていない場合、金融機関の相続手続きや法務局での不動産の名義変更にあたり、相続人全員の協力が必要となってしまいます。
相続発生後に遺言執行者を定めることもできますが、家庭裁判所での遺言の検認の手続き後に、家庭裁判所で遺言執行者選任の申立てをする必要があり、遺言内容の相続手続きは実現まで手間がかかるものとなってしまいます。
このため、遺言書は使用せず相続人間での合意ができれば遺産分割協議書での相続手続きを選ぶ相続人が少なくありません。
遺言執行者は未成年と破産者以外であれば誰を指定してもかまいませんが、最終的に家庭裁判所が選任してもらうことになります。
通常は財産を譲り受ける相続人・受遺者本人や遺言書作成に関与した専門家(司法書士・弁護士等)が指定されることが多いです。
相手の万が一に備える(予備的遺言)
予期せず遺言者より相続人や受遺者が亡くなってしまった場合、遺言はどうなってしまうのでしょうか?
遺言者には長男A、二男Bがいましたが、遺言者は老後の面倒をみてくれた長男Aに遺産の全てを譲りたいと考え、「遺産はすべて長男Aに相続させる」という遺言を残すことにしました。
二男Bとはお金の問題で親子の縁が切れている状態であり、出来る限り財産を相続させたくはありません。
ところが長男Aが遺言者より先に亡くなった場合、対象者をなくした遺言は無効になってしまいます。どうなるかというと通常の相続と同じで法定相続人へ相続されることになります。
遺言書があっても相続財産として亡くなった長男Aの相続人が受け取れるわけでありません。
このような万が一に備えるのが「予備的遺言」です。
遺言に「長男Aが先に亡くなった場合は、長男Aの子であるXに遺贈する」という一言を添えることで二男Bに財産を相続させることを防ぐことができます。
遺言書のメンテナンスをする
相続手続きのご依頼を受けて拝見する遺言書の中には「売却された不動産」、「売却された株式」等、もう存在しない財産が記載されていることがしばしばあります。
これらは現金として形をかえているだけかもしれませんが「不動産をAに」「◯◯の株式はBに」といったように、具体的に財産が特定されている形式の遺言の場合、相続発生時には該当がない財産については無効となり、遺言書を使用して手続きをすることができません。
スムーズに相続手続きできるようにとお金をかけて公正証書で遺言書を残したにもかかわらず、遺言内容が無効になってしまった部分や相続手続きできない部分に関しては、相続人全員が関与して遺産分割協議書を作成するケースもあります。
相続財産だけではなく、人間関係も変化があるものです。
すでに絶縁している親族が受遺者となっている古い遺言書が出てきてしまい、トラブルになってしまった事例もあります。
遺言書は数年に一度見直し、必要であれば書き直し、古いものは処分しましょう。
このようにちょっとした見落としが遺言を実現させる妨げとなることがあるため、遺言書は専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~19:00(土日祝を除く)
事務所名:東京国際司法書士事務所
中野駅南口改札を出たら、すぐ右に曲がり、びゅうプラザを右手に直進します。 大通り(中野通り)に出たら、セブンイレブンの方向へ渡り、線路沿いの道を進みます。そのまま直進し、ファミリーマートのあるT字路を左へ。 さらにまっすぐ進むと、左手にタイ料理屋、右手に東京CPA会計学院が見えてきます。その隣のビルが東京国際司法書士事務所です。
このサイトの監修について

- 東京国際司法書士事務所 代表司法書士 鈴木敏弘が監修
当サイトの情報は、司法書士の実務経験に基づき監修・発信されています。
相続税申告から不動産・預貯金の名義変更など、相続手続きにお悩みの方はお気軽にお問合せください。
免責事項
当サイトは、はじめての相続で何から進めたらいいのかわからないといった方へ向けて情報発信しています。
相続に関する最新の法律、判例等の情報をできる限り収集して作成しています。
ただし、相続に関する法律は、毎年のように改正されているので相続手続きや相続税に関する個別の判断については、必ずしも保証するものではありません。
当サイトの情報から発生した損害に関して、当サイトの運営元である東京国際司法書士事務所は一切の責任を負いませんのでご注意下さい。
正式にご依頼いただいたお客様に関しては、当然に責任を持って対応しておりますのでご安心ください。
- はじめての相続
- 事務所紹介